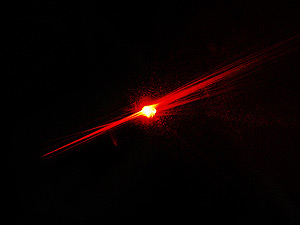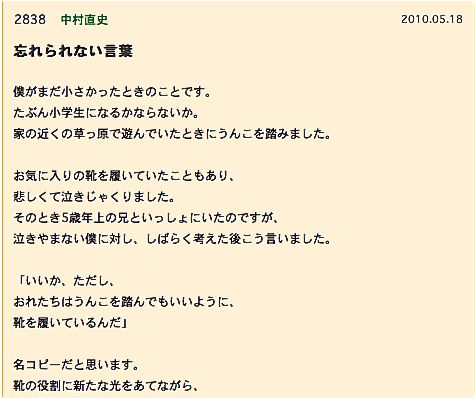詩人、立原道造。
たった24年と8カ月の人生に
紡ぎ出された彼の詩は
どこまでも青く甘く切ない。
「裸の小鳥と月あかり
郵便切手とうろこ雲
引き出しの中にかたつむり
影の上にはふうりんそう
僕は ひとりで
夜は ひろがる」
恋は人を詩人にするとはよく言うけれど
立原道造ははじめての恋がきっかけで
そのまま、本物の詩人になってしまった。
立原道造が初めて恋をしたのは14歳のとき。
相手は親友の妹で
人一倍おくての立原は
あふれる思いを歌に託した。
「片恋は 夜明淋しき
夢に見し 久子の面影
頭にさやか」
彼女を想う詩が山と積もる頃、
少年の恋は静かに終わり
詩人としての人生が始まった。
東大の建築科に通う学生になった立原道造は
ある日、大学の正門前で
太宰治にばったり会った。
「浅草にでも行かないか」と誘う太宰。
太宰の目当てはもちろん遊郭。
そんな目的を知ってか知らずか
立原は恥ずかしそうに顔を赤らめ
設計図を引くための大きな三角定規を片手に
そそくさとその場を立ち去る。
どこまでもきまじめな、立原。
すでに無頼を地でいく、太宰。
昭和十年。
まだ日本が戦争へと駆け出す前の
文学者たちの青春がそこにある。
詩人であり建築家でもあった
立原道造。
大学を出て
建築事務所に勤め始めた彼は
そこで19歳のタイピスト、
水戸部アサイと出会う。
二人の恋はどちらかといえば
消極的なものだった。
デートといえば
なぜか同期の武(たけ)さんが
いつもついてくる。
難しい文学論や自作の詩を
延々と語り続ける立原を
アサイは黙って聞いている。
ただの一度も「愛してる」とは言わなかった。
ただの一度も「愛してる?」とは聞かなかった。
病に蝕まれていく体が告げる
そう長くない将来。
言葉にすることの重さを
詩人は誰よりも知っていた。
出征する兵士たちを
戦地へ見送る万歳三唱がこだまする
昭和13年の暮れ。
立原道造はすでに結核におかされていた。
絶望と病苦の中で、
立原道造は長崎に旅に出る。
「しづかな、平和な、光にみちた生活!
そのとき僕が文学者として
通用しなくなるのなら
むしろその方をねがう。」
芥川も、中也も、
みんないなくなってしまったけれど、
夭折の詩人、なんて死んだ後に称賛されるより、
たとえ詩が書けなくなっても
いま生きてることの方が素晴らしい。
立原はただ生きたかった。
生きてやりたいことが
もっともっとあった。
昭和14年、3月。
詩人、立原道造は、
結核の療養所にいた。
食欲はとうになかったけれど
見舞いに来た友人たちに
何が食べたい?
と聞かれた立原はこう答えた。
「五月のそよ風をゼリーにして
持って来てください。」
それは
中原中也賞を受賞したばかりの
24歳の詩人の最後の言葉として
伝えられている。
立原道造が亡くなって70年。
初めての恋人であり
最後の恋人であったアサイさんは
いま長崎に住んでいる。
そこは
立原が死の病をおして
たどり着いた最後の場所。
当時のことはよく覚えていないんだけど、
と笑うアサイさん。
ツイードのジャケットに白いシャツ、
すらりと伸びた長い指と物憂げな表情。
アサイさんの手には今でも
立原から送られた15通の手紙が
そっと握られている。
「夢みたものは ひとつの愛
ねがつたものは ひとつの幸福
それらはすべてここに ある と」
ふたりは結婚することはなかったけれど
立原道造のそばには最後までアサイさんがいた。