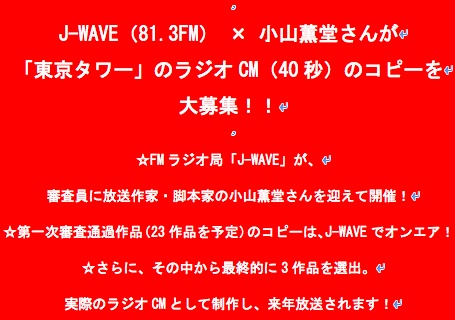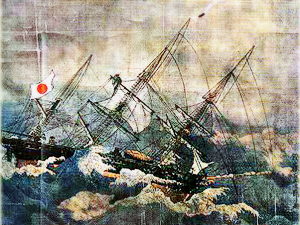ランス・アームストロングの『母』
病気で死ぬこととレースで負けることは、
私にとっては同じことだ。
そう言って癌を克服した後、
世界最大の自転車レース『ツール・ド・フランス』で
前人未到の7連覇を成し遂げた男がいる。
ランス・アームストロング。
その不屈の精神を養ったのは、
幼い頃母に言われたこんな一言だった。
あらゆるマイナスをプラスに変えなさい。
昔の傷や屈辱は張り合うエネルギーの元になる。
この世で一番大切な人の名を聞かれると、
彼は真っ先に母の名を挙げるという。

ランス・アームストロングの『癌』
癌を乗り越え、『ツール・ド・フランス』で
史上初の7連覇を成し遂げた男、ランス・アームストロング。
病魔が彼を襲ったのは弱冠25歳の時。
当時彼は世界ランクで1位を獲得し将来を大いに期待されていた。
しかし医師が下した診断は残酷だった。
病名は精巣腫瘍。既に肺と脳にも転移しており、生存確率は50%。
ベッドの上でランスは毎日自分に問い続けた。
もし生き残れるとしたら、
自分は一体どんな人間になりたいのか。
そして彼は過酷な化学療法と脳の手術を受け、
プロの自転車選手として生き続ける道を選んだ。
復帰後、彼は
癌は僕の人生に起こった最良のことだ。
と語った。
主治医が後に語ったところによると、
彼の生存確率は実はたったの3%だったという。

ランス・アームストロングの『山道』
癌から生還し、世界で最も過酷な自転車レース
『ツール・ド・フランス』で史上最多の7冠に輝く男、
ランス・アームストロング。
彼が特に強さを発揮したのは山道のコースだった。
従来の重いギアをゆっくり踏む走り方とは正反対の、
軽いギアでペダルの回転数を上げる走法で、
ランスは2位とのタイム差を積極的に広げた。
後にこの走り方は、
エネルギー効率や筋肉への負担軽減の点で優れていることが証明されたが、
彼の強さの秘密は、何と言っても癌との闘病で得た強靭な精神力だった。
闘病生活を振り返って、彼は言う。
僕には自分の人生全体が見えた。それは単純なことだった。
僕の人生は長くつらい上り坂を上るためにある。

タッカーの『アメリカンドリーム』
1945年、春。
第二次世界大戦の勝利を目前に控え、
アメリカのルーズベルト大統領はある決断をした。
増えすぎた国内の軍需工場を、
既存の大メーカーではなく中小企業に貸し出すというのだ。
どんな大企業も最初は無名の人物によって始まった。
自由競争こそアメリカンドリームである。
ルーズベルトはそう考えた。
ミシガン州出身のカーデザイナー、
プレストン・トマス・タッカーもその恩恵に預かった一人だ。
かつては爆撃機のエンジンを製造していた
シカゴにある世界最大の工場を借りた彼には、
理想のクルマを人々に提供したい。
という夢があった。
数年後、彼の夢は、当時の常識では考えられないほど画期的で、
時代を遥かに先取りしたクルマとして実を結ぶことになる。

タッカーの『トーピード』
1948年、ミシガン州出身のカーデザイナー、
プレストン・トマス・タッカーが作ったクルマは世間の度肝を抜いた。
未来的なデザイン、3つのヘッドライトによる安全性の確保、
アメリカ初の後輪駆動がもたらす運転性の向上など、
全てが当時の水準では考えられないほど先進的であった。
彼はそのクルマを「トーピード‐魚雷‐」と名付けた。
トーピードは発表されるや否や大反響を呼び、多くの問い合わせが殺到した。
しかしその出現を脅威に感じた、
フォード、GM、クライスラーのビッグ3は露骨な妨害工作を開始。
タッカーはありもしないクルマを売りつけたとして、
詐欺罪をでっち上げられ告訴されてしまう。
被告人となったタッカーは、裁判の最終弁論で訴えた。
もし大企業が斬新な発想を持った個人を潰したなら、
進歩の道を閉ざしたばかりか自由という理念を破壊することになる。
こういう理不尽を許せば、いつか我々は世界のナンバーワンから落ち、
敗戦国から工業製品を買うことになるだろう。
翌年、タッカーは無罪を勝ち取ったが、会社は倒産。
トーピードはわずか51台しか生産されず、幻の名車となってしまった。
しかしそのうちの47台が今も現役で走り続けていることは、
タッカーの先見性がいかに高かったかを証明している。
最終弁論でタッカーがした予言は、
やがて日本車とドイツ車の台頭により現実のものとなった。

ミッキー・ロークの『レスラー』
80年代、セックスシンボルの名を欲しいままにした俳優ミッキー・ローク。
しかしその後は薬物中毒や整形手術の失敗などゴシップばかり。
キャリアも私生活も、ルックスまで失った彼のもとに、
ある日一本の脚本が届いた。
50を過ぎても現役を続けるかつての人気レスラー、ランディ。
家族には見放され、長年の無理とドラッグで体はぼろぼろ。
心臓発作を起こし、医者から廃業を勧告される。命の危険がある、と。
引退して私生活を立て直そうと試みるランディ。しかしうまくいかない。
やがて彼は自分にはプロレスしかないことを悟り、
命と引き換えにかつての輝きを取り戻そうとする。
まるで自分の人生のような話に、ロークの心は昂ぶった。
もしこの仕事をしくじったら、
オレは俳優としても、人間としても終わってしまう。
10数年ぶりのチャンスに、ロークは死に物狂いでくらいついた。
夜遊びもきっぱりやめ、数か月に及ぶ厳しいトレーニングにも耐え抜いた。
結果、この映画「レスラー」はベネチア映画祭で最高賞を獲得、
ローク自身もアカデミー主演男優賞にノミネートされる快挙となった。
映画のラストでランディは
あそこが俺の居場所だ。
と呟き心臓をおさえながらコーナーポストから跳ぶ。
果たして彼は死んだのか。それは誰にもわからない。
しかしロークは再びリングに舞い戻り、見事甦った。

AC/DCの『ベストアルバム』
全世界のアルバム総売上は2億枚を超え、
1980年に発表した「Back in Black」が、
マイケル・ジャクソンの「スリラー」に次いで
歴代2位の売上記録を持つ
オーストラリア出身の世界的ロックバンド、AC/DC。
40年近く第一線で活躍し続けてきた彼らだが、
意外にもまだやったことのないことがある。
ベストアルバムを出したことがないのだ。
その理由をフロントマンのギタリスト、
アンガス・ヤングに尋ねると、
ファンが持っている曲を
もう一度買わせるようなことはしたくないし、
アルバムそれぞれに個性があるから
それを壊すような売り方はしたくないんだ。
と、何とも律義な答が帰ってくる。
世界一のロックバンドは、世界一ファン想いでもある。