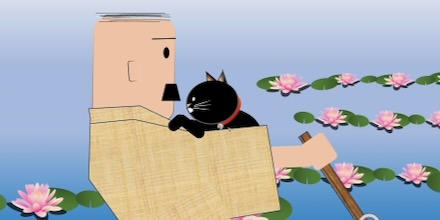人気教師の夢
ストーリー 福里真一
出演 遠藤守哉
その30年以上にわたる教師生活を通して、
彼はずっと人気教師だった。
いつも明るく楽しい冗談で、
生徒たちを笑わせた。
若い頃は爽やかでなくもないルックスで、
女生徒からもモテたらしい。
悩みや問題を抱えた生徒には、
見放すことなくきちんと向き合った。
時には生徒の側に立って、
頑固すぎる校長や学年主任と、
戦うことも辞さなかったらしい。
彼のわかりやすい物理の授業の影響で、
多くの生徒が理系の大学を目指すことになった。
バレーボール部の顧問として、
チームを全国大会出場に導いたこともあった。
そんな人気教師が、
定年を前に退職することになった。
卒業生有志が企画した送別会には、
数多くの元生徒たちが集まった。
感謝のこもった目で見つめる元生徒たちの前で、
彼が語ったのは、
しかし、少し意外な話しだった。
「オレは若い頃から、
ずっと長距離トラックのドライバーに憧れていた。
子供の頃、
『トラック野郎』という映画で、
デコトラで旅する菅原文太さんに出会って以来、
ずっとトラックドライバーになるのが夢だった。
教師をやりながらも、いつかはトラック野郎になりたいと、
思い続けていた。
いま、60歳を前にして、年齢的に最後のチャンスだと思い、
履歴書をもって、運送会社を回った。
そして、ようやく採用してくれる会社が見つかった。
この年末から、いよいよオレの長年の夢がかなうんだ」
人気教師は、
生徒に冗談を言い、女生徒から憧れられ、
悩みや問題がある生徒に向き合い、
校長や学年主任と戦っている間も、
ずっと心の中では、
長距離トラックのドライバーを夢見ていた。
物理を丁寧に教え、
バレーボールで生徒たちを鍛えあげている間も、
ずっとずっと、トラック野郎になりたかった。
そのことを、元生徒たちが知ったとき、
それまであたたかみにあふれていた送別会の会場に、
一瞬、シラーッとした空気が流れたのは、
間違いがないことだった…。
2026年がやってきた。
物流に正月休みはない。
人気教師が運転するトラックは、
今ごろ、
海沿いのまっすぐな道を走っているのか、
曲がりくねった山道を登っているのか、
あるいは、吹雪の中を疾走しているのかもしれない。
「夢」という名の「思いこみ」が、
今年も多くの人の人生を動かしていくことだろう。
そんなことを考えながら、私はいま、
おそらく長距離トラックによって運ばれたであろう、
おせちのかずのこを、たべている。(おわり)
.
出演者情報:遠藤守哉