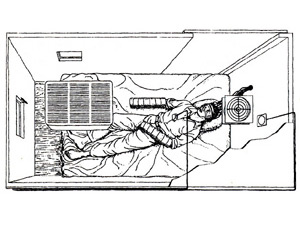日本の色 フジタの白
グラン・フォン・ブラン
すばらしい肌の白
1920年代パリに渡った日本人画家、
藤田嗣治が描いた「寝室のキキ」に寄せられた賛辞だ。
フジタは、浮世絵で表現されている
肌の白さや黒の輪郭線を再現することが、
日本人画家としての独自性になると考えた。
浮世絵の白を表現するために、
キャンバスに木綿のシーツのような
やわらかな生地を張り、
何種類もの顔料を使って白を描き出し、
最後にてかりを抑えるために
タルカムパウダーを用いた。
独自性を出すには、独自の方法が必要だった。