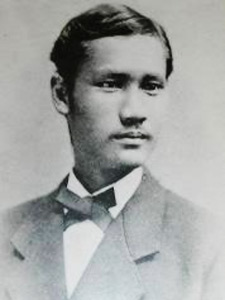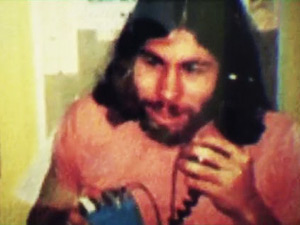Abhisek Sarda
文豪の朝食 夏目漱石
明治の文豪、夏目漱石は、
当時としては珍しい洋風の朝食を好んでいた。
ロンドン留学から帰国した後、
彼の朝食はもっぱら、紅茶とトースト。
そして、何よりも楽しみにしていたのは、苺のジャム。
大の甘党で、
羊羹を常に持ち歩くほどだったと言われる漱石は
ジャムをトーストに塗るのではなく、
瓶からスプーンですくってそのまま食べていたらしい。
代表作『吾輩は猫である』には、
猫の飼い主が、ジャムを食べすぎて妻に咎められるシーンがある。
元来ジャムは幾缶舐めたかい?
今月は八つ入りましたよ。
〜あんなにジャムばかり嘗めては、胃病の治る訳がないと思います。
この言葉は、漱石が実際妻に言われたものだろうか。
それとも、糖尿病のけがあった自分への戒めの言葉だったのだろうか。