
Bjorn Hermans
円空と木喰 7
木喰は、
広葉樹を好んで使ったという。
やわらかくきめの細かい
広葉樹の木肌が、
曲線だけでつくられる作風に
生かされている。
円空は、
建築材の切れ端、朽ち木、
果ては流木に至るまで、
仏像の材料を選ばなかったが、
どちらかと言えば針葉樹を好んだ。
鉈で割りやすい針葉樹は、
直線的で荒削りの作風に
適していたと思われる。

Bjorn Hermans
円空と木喰 7
木喰は、
広葉樹を好んで使ったという。
やわらかくきめの細かい
広葉樹の木肌が、
曲線だけでつくられる作風に
生かされている。
円空は、
建築材の切れ端、朽ち木、
果ては流木に至るまで、
仏像の材料を選ばなかったが、
どちらかと言えば針葉樹を好んだ。
鉈で割りやすい針葉樹は、
直線的で荒削りの作風に
適していたと思われる。

Tsuyoshi Adachi as thin-p
円空と木喰 8
大正の終わりから昭和初期にかけて
活躍した彫刻家、橋下平八は、
あるとき円空仏に出会って衝撃を受ける。
「碧玉の如き清浄無垢とそれを作出する
精神の明澄さ、その技能の洗練。」
と、橋下平八の日記にある。
近代の彫刻家は円空仏の自在な鑿使いと
無垢な精神性に惹かれた。
同じ頃、日常の美を提唱した
民藝運動で知られる柳宗悦は、
四国の寺で木喰仏を発見する。
「私は彼を日本が産んだ最も独創的な
仏師として記念することを躊躇しない。」
そう柳は書いている。
けれども、円空も木喰も
芸術品をつくったわけではない。
人々の苦しみを身代わりになって
背負う、実用品としての仏像。
その造形が美しいとしても、
作者の意図するものでは
必ずしもなかっただろう。
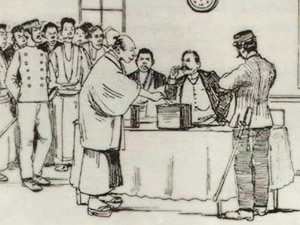
尾崎行雄の95年 ①
1890年、明治23年、7月1日。
第一回衆議院選挙がおこなわれた。
投票できるのは、25歳以上の男子だけ。
それも15円以上の納税者に限られた。
有権者数約45万人。当時の日本の人口の
わずか1.1%にすぎなかった。
それがわが国初の選挙だった。
このとき当選した300人の議員の中に、
32歳の尾崎行雄がいた。
三重県第5区から立候補。
有効投票数1,919票のうち1,772票を
得てトップ当選を果たした。

尾崎行雄の95年 ②
明治維新の10年前、
相模国津久井郡で生まれた尾崎行雄は、
討幕運動に奔走した父の薫陶を受け、
福沢諭吉の慶応義塾に学んだのち、
新聞記者を経て、明治政府の官僚となる。
早くから政治への志を抱いた尾崎は、
やがて自由民権運動に身を投じ、
大隈重信と共に立憲改進党をつくる。
薩摩と長州。
明治維新の原動力になった2つの藩出身の
人間だけが優遇される政府のあり方に
疑問をもった尾崎行雄は、
欧米をお手本とする国会の設立、
選挙制度の確立を実現し、
理想の政策を共にする者があつまってつくった
政党が政治を動かす議会政治をめざした。
1889年にようやく国会が開設され、
1890年におこなわれた第一回衆議院総選挙で
当選。尾崎行雄のほんとうの戦いは
ここから始まる。

尾崎行雄の95年 ③
咢堂・尾崎行雄。別名、憲政の神様。
1890年、32歳で第一回衆議院総選挙で当選して以来、
1953年、95歳で落選するまで、25回連続当選。
63年の長きにわたって国会議員の職にあった。
尾崎行雄の生涯をたどることは、
議会政治の歴史を知ること。
1891年の第二回総選挙で、
政府の露骨な選挙干渉がおこなわれ、
票の売買がはびこったときも。
高額納税者だけに与えられていた選挙権の
制限を撤廃する普通選挙の運動が
燃えさかったときも。
日清・日露の両戦争で発言権を増した
陸海軍が国会に軍備増強を突きつけたときも。
国会にはいつも尾崎行雄がいて、
つねに正論を唱え、政府の方針を糾していた。
やがて泥沼の戦争に向かう1940年代、
自らの基盤としていた政党が、こぞって
大政翼賛会に合流し戦争遂行に走った時代にあっても、
尾崎行雄だけは政府非推薦をつらぬいて当選し、
国会議員でありつづけた。
太平洋戦争が終わった翌年、
女性が初めて選挙権を手に入れた。
1890年の第一回総選挙から数えて22回目。
この国が初めて経験する完全普通選挙だった。
この年。尾崎行雄、88歳。政界引退を決めていたが、
支持者が許さず、またもや当選。
連合国による占領下の日本は、まだ尾崎を必要とした。
そして、今日、2012年12月16日。
第46回衆議院総選挙。地下に眠る憲政の神様は、
いまの政治家に何を思うだろう。

左手の話 ①レオナルド・ダ・ヴィンチ
レオナルド・ダ・ヴィンチは
左利きだった、という説がある。
数多く残されたデッサンをよく見ると、
斜線の筆致が、ほぼすべて、
左上から右下の方向に走っている。
右利きの人間がそのような方向へ
筆を運ぶのは不自然であり、無理がある、
というのが、ダ・ヴィンチ左利き説の
根拠になっている。

左手の話 ②宮本武蔵
宮本武蔵は、
絵を描くのが好きだった。
その腕前は、武芸者の余技を
はるかに超えるものだった。
彼が残した水墨画の
墨の濃淡から、
宮本武蔵は左利きだった、
と唱える人がいる。
武蔵が描く線は、
右側が濃く、左側が薄いことが多い。
筆で線を書いてみるとわかるが、
右利きの人間ならその逆になる。
このあたりから、
宮本武蔵は左利きだった、
という説が生まれた。
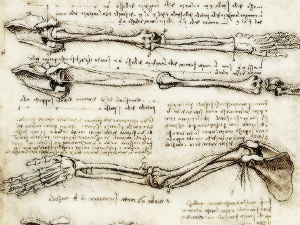
左手の話 ③天才たち
人間の脳は左右に分かれていて、
右脳が左半身を、左脳が右半身を司っている。
左右が交差するかたちだ。
右脳は音楽脳とも呼ばれ、
視覚・聴覚などの五感を認識し、
空間認知なども受けもっている。
左脳は言語脳とも呼ばれ、
言葉や文字などを認識し、
論理的な思考に展開する。
左利きの人は左手をよく動かすので、
右脳の働きが活発になり、
結果、感性が豊かになる。
天才に左利きが多いのはそのためだ、
と主張する向きもあるが、
科学的な根拠はなく、俗説の域を出ない。
ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、
ニュートン、ベートーベン、
アインシュタイン、ピカソ…。
左利きだったと伝えられる
そうそうたる天才たちの名を並べると、
左利き天才説を信じたくなってくるのだが。

左手の話 ④ジョージ6世
『英国王のスピーチ』という映画がある。
英国王ジョージ6世が吃音症を克服する
姿を描いてアカデミー賞を獲った。
左利きだった王は幼少時、
父・ジョージ5世から左利きを
むりやり矯正される経験をもつ。
食事のとき、息子の左手に
長い紐を結びつけ、左手を使った場合、
父が乱暴に引っ張って注意した。
この幼児体験がジョージ6世を
ストレス過多にし、内向的にし、
吃音症に悩む原因になったといわれている。
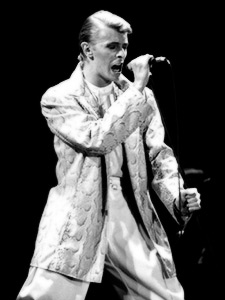
Helge Øverås
左手の話 ⑤デヴィッド・ボウイ
「左手で絵を描いたり字を書いたりすると、
まわりの連中が『こいつは悪魔だ!』と、
私をからかったことを、
いまでもはっきり覚えている」
そう語ったのは、デヴィッド・ボウイ。
左利きであるだけで差別を受けた
みずからの経験。
こんなことも語っている。
「教師は右利きにさせようとして
私の手をひっぱたいたものだ。
そう、かつてはイギリスでも
左利きは忌まわしいものとされていたんだ」
左利きをむりやり右利きに直されたのは、
英国王だけではなかった。
箸をもったり、鉛筆をつかったりするのは
右手で。という社会通念が、
かつて日本にもあった。漢字もひらがなも
右手で書くことを前提につくられている。
左手で毛筆をもって縦書きの文字を綴るのは
なかなか難儀なこと。そんな文化のありようが
左利きをあまり歓迎しなかった。
英国の場合、宗教上のなんらかの理由もあり、
左利きの存在をゆるさない空気があった。
Copyright ©2009 Vision All Rights Reserved.