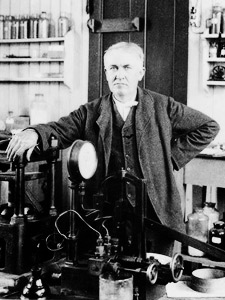Kennosuke Yamaguchi
先輩! 山口瞳
4月1日。
多くの企業で入社式が開かれるこの日に合わせ、
毎年掲載される新聞広告がある。
「新入社員諸君!」の一文ではじまるこの広告。
1978年の開始からその死の前年である94年まで、
直木賞作家山口瞳が20年近くに渡り筆を執った。
山口は先輩社会人を代表して
新社会人へ言葉を送り続けた。
たとえば、社会人としての酒の飲み方。
まず、酒は愉快に飲めと言いたい。
愉快に飲むためには、他人に迷惑をかけてはいけない。
迷惑をかけないためには、酒を飲んでいるときに、
絶対に他人のことに口を出さないことだ。
来る年も来る年も、
山口の言葉に、新入社員は勇気づけられ、
先輩社会人たちは深くうなずいた。
山口が担当した最後の原稿には、こんな言葉が書かれている。
踏み込め、踏み込め、失敗を恐れるな!