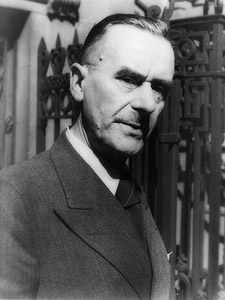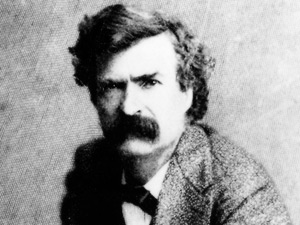
三島邦彦 マーク・トウェイン
児童文学の名作『トム・ソーヤーの冒険』。
その8年後、作者のマーク・トウェインは続編となる
『ハックルベリー・フィンの冒険』を書きあげた。
ただし、書き上がったのは児童文学ではなく、
アメリカ文学史に輝く文学作品だった。
もはや子どもむけの物語ではない。
そのことを示すため、
トウェインは物語をこのような警告から始めた。
警告
この物語に主題を見出そうとする者は起訴される。
教訓を見出そうとする者は追放される。
筋を見出そうとする者は射殺される。
著者の命により 兵站部長G・G