
登場人物たち コペルくん(吉野源三郎『君たちはどう生きるか』)
吉野源三郎の本、『君たちはどう生きるか』。
友だちを裏切ってしまい、心を痛める主人公のコペル君に、
仲良しのおじさんはこう伝えます。
僕たちは、その苦痛のおかげで、人間が本来どういうものであるべきかということを、
しっかりと心に捕えることができる。
心が痛む時。それは、大事なことを学ぶチャンスの時かもしれません。

登場人物たち コペルくん(吉野源三郎『君たちはどう生きるか』)
吉野源三郎の本、『君たちはどう生きるか』。
友だちを裏切ってしまい、心を痛める主人公のコペル君に、
仲良しのおじさんはこう伝えます。
僕たちは、その苦痛のおかげで、人間が本来どういうものであるべきかということを、
しっかりと心に捕えることができる。
心が痛む時。それは、大事なことを学ぶチャンスの時かもしれません。

登場人物たち 女房(古今亭志ん生『厩火事』)
昭和の名人、古今亭志ん生。
彼の落語に出て来る夫婦は、いつもケンカをしてばかり。
ある時、働きもせず家で寝てばかりの旦那に業を煮やした女房が、
大家さんに旦那の悪口を言いつける。
あきれた大家さんは、そんな旦那とは別れてしまえとすすめる。
すると急にもじもじし、歯切れが悪くなる女房。
なんで別れないんだ、と聞く大家さん。
すると一言、
だって、寒いもん。
落語の世界の人々は、ケンカするほど仲がいい。

Jonas Hansel
おいしいはなし / 荒木水都弘(あらき みつひろ)
日本一予約のとれない鮨屋、「銀座 あら輝」。
店主・荒木水都弘は、
孤高な芸術家のように鮨と向き合う。
そして語る。
何かを成し遂げたいと思うならば、
完璧に孤独にならなければいけないんじゃないでしょうか。
やはり、ひとりで崖っぷちに立たなくては
見えてこない世界ってあるんだと思います。

Cult Gigolo
おいしいはなし / ループレヒト・シュミット
人生最後の食事には、何を食べたいですか。
ドイツのハンブルグにある「ロイヒトフォイヤー」というホスピス。
入居者たちが人生の最後の時を過ごすこの場所で、
料理長ループレヒト・シュミットは毎日、
その人にとって最後になるかもしれない料理を作っている。
入居者たちからは、記憶の中にあるおいしかったものを頼まれる事が多い。
若い入居者からハンバーガーとフライドポテトを頼まれることもあれば、
「思い出のスープを。」というリクエストも。
本人や家族からその味について詳しく話を聞き、
「この味じゃない」と言われては、何度も試行錯誤を繰り返す。
その料理が複雑でも簡単でも、何度文句を言われようと、
うまく作れるまでとにかくやるんですよ。
後悔するのは全力を尽くせなかったときだけです。
「料理よりも人間としての修業になるといいかな。」そう言って、
ループレヒトは今日も厨房へと向かう。

suga*memo
おいしいはなし / 平松洋子(ひらまつ ようこ)
エッセイストの平松洋子は、
日常に発見をもたらす天才だ。
かまぼこは手でちぎる。
盛り付けにガラスのコップを使ってみる。
たくあんの切り方を変える。
豆腐にオリーブオイルをかける。
彼女の言葉を信じてみれば、食卓は今までと違う姿を見せる。
一手間、一工夫が、ふつうの毎日をちょっと新鮮にしてくれる。
彼女は言う。
ふつうがおいしければ、それでじゅうぶんだ。
なんの力みも入っていなくて「ここ一番!」の特別感なんか全然なくて、
でもおなかの底から「ああ、おいしかった楽しかった」。
そう思えればいうことなし。

suiryuukawase
自然と人 坂東元(ばんどうげん)
野生動物の行動様式に合わせた展示方法、
「行動展示」で有名な旭山動物園。
そこにはペットでも家畜でもない、
野生動物の誇り高い生き様に触れてほしいという理念がある。
副園長で獣医の坂東元さんは
野生動物を「すごいヤツら」だと言い、こう語る。
「すごいヤツら」の尊厳を守るために、ぼくはこの一生を捧げたい。

自然と人 石牟礼道子(いしむれ みちこ)
『苦海浄土(くがいじょうど)』という本がある。
作者は、石牟礼道子(いしむれ みちこ)。
水俣市で主婦をしながら書きためたこの作品は、
水俣病患者たちを描く澄んだ筆致とリアリティが高く評価され、
ノンフィクションの傑作として第一回大宅壮一賞を受賞した。
しかし、石牟礼はこの賞を辞退する。
水俣病は人間の原存在の意味への問いである。
そう語る石牟礼が台所の片隅で日々筆を執った切実さ。
沈黙に光を射し、患者たちの心を代弁すること。
それが彼女の求めるすべてであり、
それ以上は何も必要なかった。
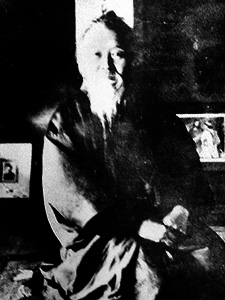
自然と人 田中正造(たなかしょうぞう)
その人は今も歴史の教科書の挿絵の中で
警察官に組み伏せられながら何かを訴えている。
名前は、田中正造。
衆議院議員の正造はある日、
栃木県の足尾銅山のふもとにある
村の死亡率が異様に高まっていることを知る。
村を流れる渡良瀬川では魚たちが死に、
森の木は枯れはじめているという。
正造は、これを一生の一大事とした。
十年に渡り議会で鉱毒問題を扱ったが
状況は改善できなかった。
議員活動の限界を感じると、
財産をすべて寄付し、
鉱毒に苦しむ人々の村へと入っていった。
村人の家を転々としながら、
村人の立場で鉱毒問題に取り組んだ。
近代文明の本質にある闇を、正造は鉱毒問題に見ていた。
正造の日記には、こんな言葉が書かれている。
真の文明は 山を荒さず 川を荒さず 村を破らず 人を殺さざるべし

ヤマザキノブアキ
夏の終わりに 安野光雅(あんのみつまさ)
1945年の夏の終わり。
19歳の青年が、靴下いっぱいにつめた米を手に、
軍隊から両親の住む家へと帰ってきた。
出征の時に
両親と別れた峠に再びやって来ると、
ふもとの野原には曼珠沙華が一面に咲いていた。
わたしは着ていたものをすべて脱いで煮沸し、
シラミの卵を退治して、やっと兵隊というものから、
普通の人間に戻ったのだと思っている。
青年はこうして自分の日常を取り戻していった。
焼け跡のぼろぼろになった街を歩きながらも、
安野の目には明るい未来がほのかに見えていた。
絶望に似た不思議な混沌から、
何かが芽生えてくる期待だけがあった。
青年の名前は、安野光雅。
豊かな色づかいとやわらかなタッチの水彩画で、
画家として、絵本作家として、
後に海外からも高い評価を受けることになる。
その夏の終わりは
日本中で新しい季節が始まろうとしていた。

夏の終わりに 堅田外司昭(かただ としあき)
1979年の夏の甲子園。
和歌山の箕島高校と
石川の星稜高校の延長戦は
星陵が2度のリードを守れず
最終イニングの18回へ。
両校とも体力は限界に達し、
決着は翌日の再試合に持ち越しかと思われた。
しかし、18回の裏、
星陵の堅田投手が投げた208球目が打たれ、
星陵の夏は突然の終わりを迎える。
その日を振り返り、堅田投手は言う。
ぼくは泣かなかった。
眠れずにみんなと話し合っていたことは、
これで野球からしばらく解放されるということだった。
夏が終わるたび、球児たちは大人になる。
全力を尽くしたものだけが持つ輝きを手に入れて。

夏の終わりに 正岡子規
病の床で正岡子規は、
一年前の夏を思い出していた。
フランクリン大統領の自伝を読むことを日課にしていた夏だった。
去年はこの日課を読んでしまうと、
夕顔の白い花に風がそよいで
初めて人心地がつくのであったが、
今年は夕顔の花がないので暑苦しくて仕方がない。
晩夏の厳しい日射しの中で、
子規の最後の夏が
ゆっくり終わろうとしていた。
Copyright ©2009 Vision All Rights Reserved.