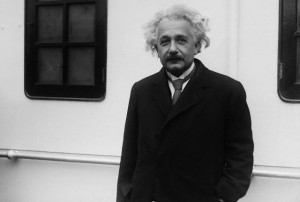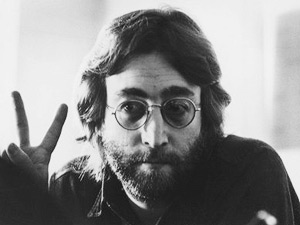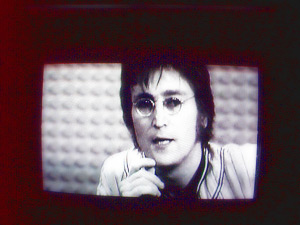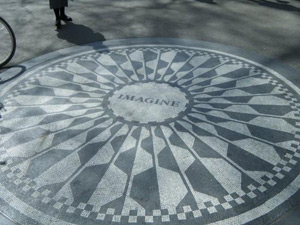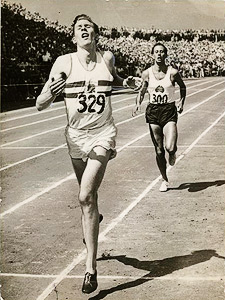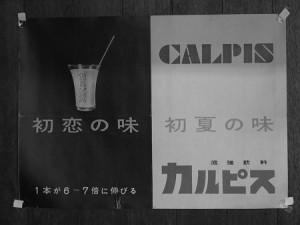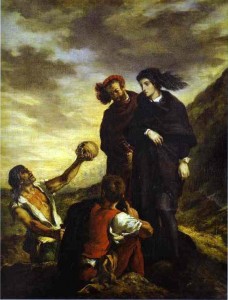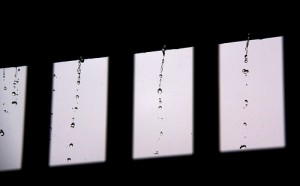人と、壁。/ラスコーの洞窟壁画
歴史的な発見のきっかけは、
犬が穴に落ちたことだった。
1940年9月12日。
フランスのある田舎町の森の中で、
少年たちが犬と遊んでいた。
森には数年前の落雷で空いた穴があり、
そこに犬が落ちてしまったのだ。
犬を助けようと穴に降りると、
穴は、洞窟につながっており
少年たちはその壁に牛や馬、鹿の絵を見つける。
ラスコーの洞窟壁画発見の瞬間だった。
一万五千年の時を経て、洞窟の壁が、
少年とクロマニヨン人を結びつけた。
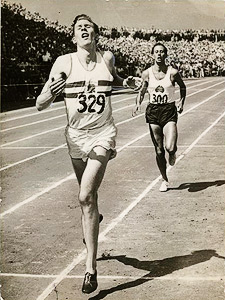
人と、壁。/ロジャー・バニスター
1マイル、約1609メートル。
半世紀前、この距離を4分以内で走ることは、
人類が決して越えられない壁だと言われていた。
あるスポーツ記者は、
「人類が南極点と北極点に到達し、
ナイル川の源流を発見し、海の最深部に達し、
未開のジャングルを踏破した現在も、
1マイル4分という領域はいまだ未踏のまま、
多くの者たちの努力を拒み続けている。」という記事を書いた。
ある医者は、1マイル4分は人体の限界であり、
その挑戦は生命に危機を及ぼすこともあると警告を発した。
しかし、その壁は破られた。
1954年、イギリスの大学生ロジャー・バニスターが、
1マイルを3分59秒4で走り抜けたのだ。
この2ヶ月後、
ジョン・ランディという選手が3分58秒0の世界新記録を出し、
つづく1年の間に23人ものランナーが1マイル4分の壁を破った。
誰かが壁を超えたとき、そこにもう壁はなくなる。
ロジャー・バニスターは、
1マイル4分の壁から人類を自由にしたのだ。

人と、壁。/ウォーレン・バフェット
ニューヨーク、ウォール街。
壁の街という名前は、この街を作ったオランダ人が
外敵の侵入を防ぐために
材木で壁を築いたことに由来する。
2008年にはビル・ゲイツを抜いて
世界の長者番付第1位に躍り出た天才投資家、
ウォーレン・バフェットは
ウォール街から1万キロ離れたところに住んでいる。
そして、こんなことを言う。
みんなが貪欲になっている時は警戒しろ。
みんなが警戒している時は貪欲になれ。
ウォール街の逆をいって富を築くのも
また壁を味方にしたといえるだろうか。

人と、壁。/富山県警山岳警備隊
山を見ると、登りたくなる。
壁を見ると、越えたくなる。
そんな登山家の聖地は飛騨山脈、通称北アルプス。
その厳しく切り立つ岩肌は、山と言うよりもはや壁。
どんなベテランの登山者でも
思わぬ事故に遭遇することもある。
しかし、そこには富山県警山岳警備隊がいる。
富山県警山岳救助隊は1965年に結成され
隊員数27人。救助した人は3,000人。
日本一の山岳警備隊と呼ばれ、
「落ちるなら、富山側へ」と言われるほど登山者の信頼は厚い。
想像を絶するような過酷な状況での人命救助の場で
人体の限界という壁に直面した時、彼らを支える言葉がある。
苦しくても、苦しくない。
彼らもまた、壁を越えているのだ。

人と、壁。/ネルソン・マンデラ
倒れている時、地面は壁になる。
壁をなくすには、立ちあがればいい。
立ちあがった時、地面は壁ではなく、道になるから。
南アフリカ共和国の元大統領、ネルソン・マンデラ。
人種の壁と闘い続けた彼は、こんな言葉を残している。
転ばないことより、
転ぶたびに立ちあがること。
そこに人生の輝きがある。
倒れることを、恐れない心。
それが、壁を道に変える極意のようです。