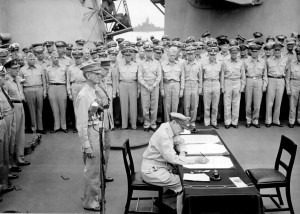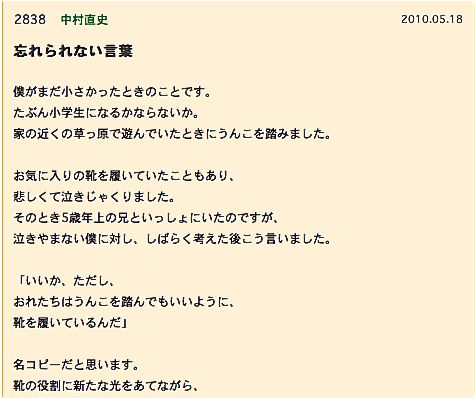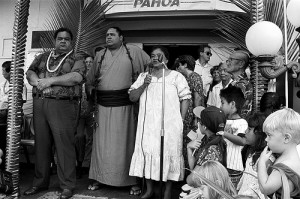えらい人はいいこと言う/アンリ・ド・レニエ
人生のすべてにおいて、
ものを言うのは経験だ。
そう思っていたら、
遠くフランスから反対意見が聞こえてきた。
「燃え上る青春」を書いた
フランスの小説家、アンリ・ド・レニエは言う。
恋には経験というものはない。
なぜならその時にはもう恋していないのだから。
恋に落ちるたび初心者に戻ってしまうなんて
困ったものだ。

えらい人はいいこと言う/タヒチ人
座右の銘は何ですか?
と聞かれて
即座に答えられる人を尊敬してしまう。
それが立派な言葉だとなおさら。
でも
座右の銘が
とっても力が抜けてる
という人のほうが
友だちになれそう、とも思う。
たとえば私の友人の
座右の銘は、
アイタ・ペアペア
タヒチ人がよく言う、
「気楽にやろうよ」。
という意味の言葉らしい。
毎日いろいろありますね。
でもまあ、アイタ・ペアペアってことで。

えらい人はいいこと言う/亀倉雄策
パソコンから目線をそらし
ふとまわりを見渡してみる。
壁、柱、CD、本、文具。
視界のすべては人工物で
人工物とはつまりすべてデザインされたものだ
と気づく。
目に映るものすべてのデザインが、
人を幸せにするほどステキならば
今日という一日も
ずいぶん変わるんじゃないか。
東京オリンピックの
ポスターをつくったことで知られる
デザイナー、亀倉雄策。
彼はそんなデザインに関する考えを
追求した人だった。
デザインとは明るい生活の歌でなくてはならない。
同感です。
だって、人生は、
明るい生活の歌に満ちていたほうがいい。

えらい人はいいこと言う/マザー・テレサ
マザー・テレサ。
・・・いま、その名前を聞いて
どんな姿を思い浮かべましたか?
貧しい人々に手を
差し伸べている姿
ではありませんでしたか?
でも、マザー・テレサが
その人々を貧しいと思っていたかどうかは疑問。
彼女にとって貧困とは別のことだった。
ほほえみ ふれあいを
忘れた人がいます。
これはとても大きな貧困です。

えらい人はいいこと言う/小津安二郎
電車に乗って中づりを眺めるだけで
情報がどっと流れ込んでくる。
お金を儲けろ
生き方を変えろ
キレイになれ
そのままの自分でいろ
これを飲め
これを買え
通勤先の駅につくころには
情報が多すぎて
何をどうすべきか
よくわからなくなっている。
そんなときは、
小津安二郎の映画を思い出してみる。
落ち着きたいときには
彼の映画を思い出すようにしているのだ。
小津さんは言った。
どうでもよいことは流行に従い、
重大なことは道徳に従い、
芸術のことは自分に従う
流されたってかまわないのだ。
大事なことで流されなければそれでよい。
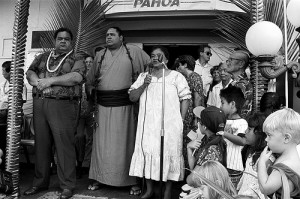
えらい人はいいこと言う/曙太郎
彼がマットに沈む姿を何度見たことか。
どうせ、負けるだろう。
やめとけばいいのに。
と思う。
でも彼が、自身のことをそんな風に
見ていたことはないらしい。
曙太郎。
関取時代のことを振り返り、こう言った。
全勝優勝は一度もなかった。
いつも、序盤戦で土を付けられた。
それでも、そこからガタガタ崩れることなく、
気持ちを入れ直して優勝をつかんできた。
それが、私の誇りだ。
これから彼を応援するときは、
きっと自分を応援するような気持ちで応援すると思う。
がんばれ、曙。

えらい人はいいこと言う/アインシュタイン
いやなニュースを聞いた。
いやなニュースを何種類も聞いた。
そんな日は人間が嫌いになりそうになる。
「でも」とアインシュタインは言う。
人間性について絶望してはいけません。
なぜなら、私たちは人間なのですから。
アインシュタインは
人生の定理も
見つけたのかもしれない。

えらい人はいいこと言う/モニカ・ボールドウィン
まいにちのことが
ちょっと憂鬱になる、
そんなとき
言葉に出会い、
何かがパッと変わることがある。
だれかが、
私の状況を見越して
わざわざ言葉を用意していたかのように。
たとえば、こんな言葉。
朝目覚めるときが二十四時間のうち最も素晴らしい、
といつも思います。
どんなに疲れ切って、やるせなくても、
きっと何かが起こるに違いないと思えるからです。
絶対といってもいいくらい何も起こらないんですが、
それでも、ちっとも構いません。
絶対に起こらないとは言えませんから。
イギリスの作家
モニカ・ボールドウィンが残した言葉です。
それでは、おやすみなさい。
そして、よい目覚めを。