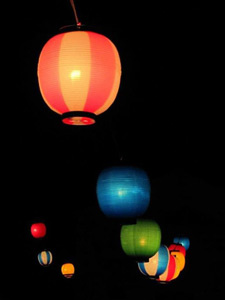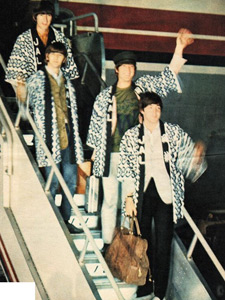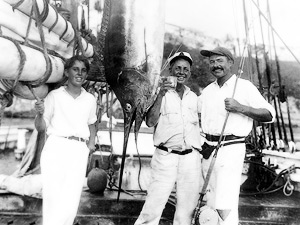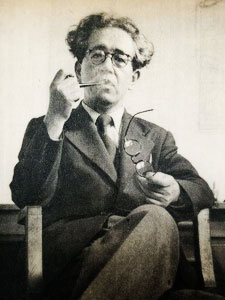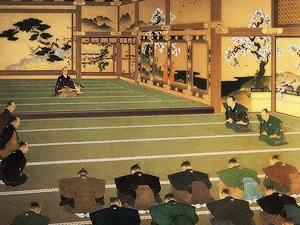
龍馬は裏方
旧暦の今日11月15日が
誕生日であり、命日とされている坂本龍馬。
好きな歴史上の人物で
必ず上位にランクインする幕末のヒーロー。
だが彼は決して時代の表舞台に
立とうと思っていたわけではない。
むしろ目立たないよう、
日本を変えるという大仕事の裏方に徹していた。
薩長同盟も、大政奉還も
龍馬が前面に立つのではなく
主役である人々を説得して、
日本の未来のために心を変えさせる。
それが彼のやりかただった。
政治家になる気がなかった龍馬は、
きっと誰よりも自由でありたかったのだ。
新しいものが好きで
日本ではまだ珍しいブーツを履きこなしていた龍馬。
もし暗殺されることなく
夢だったアメリカに渡っていたら
龍馬は、当時生まれたばかりの自由の象徴ジーンズを
最初に履いた日本人になっていただろう。