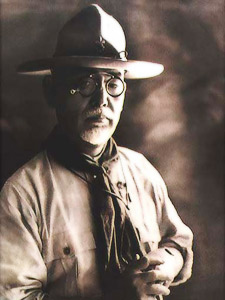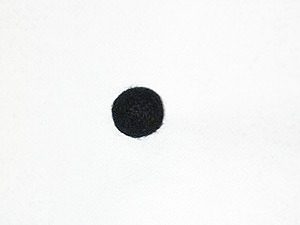
宮沢賢治と冬眠
今日9月21日は、
宮沢賢治の命日である。
詩人、草野心平に
「冬眠」という詩がある。
冬眠というタイトル以外に言葉は何もない。
ただ黒い丸がひとつ書かれただけ。
世界で最も短い詩とも言われている。
ただの記号じゃないか。
こんなものを詩と呼ぶべきではない。
1951年の発表当時、
この詩は様々な議論を呼んだ。
しかし冬眠というタイトルとともに
この黒い丸を見ていると
様々なイメージが浮かんでくる。
心平が好んで詩に描いた蛙が
その黒い丸の中ですやすやと
眠っているようにも見えてくる。
草野心平は同じ東北出身の
宮沢賢治を生前から高く評価し
死後その再評価に尽力した。
もしも賢治が長生きして
この詩を読んでいたら、
きっとにっこり笑って
心平に激励の手紙を
書いたのではないだろうか。