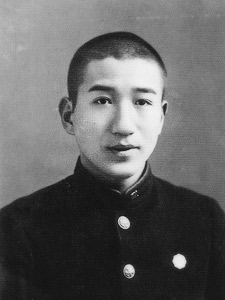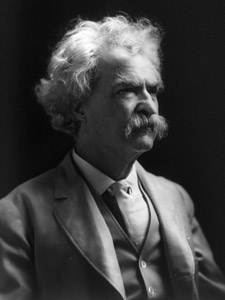考える哲学者
今日、4月27日は哲学の日。
哲学、という言葉が持つ
抽象的でとっつきづらい空気を
考える、という言葉で、
すべての人のものにしようとした池田晶子。
哲学者ではなく、文筆家と名乗り
他の哲学者たちと一線を画した池田は
2007年、46歳の若さで世を去った。
彼女は決してやさしいだけではなく、
考えることをしない世の中に、
厳しい言葉も残している。
地球人類は失敗しました。
生存していることの意味を問おうとせず、
生存することそれ自体が価値だと思って、ただ生き延びようとしてきた。
医学なども、なぜ生きるのかを問わず、
ただ生きようとすることで進歩した。
人がものを考えないのは、死を身近に見ないからだと思う。
一番強いインパクトは死です。人がものを考え、
自覚的に生き始めるための契機は死を知ることです。
精神の在り方が変わらなければ、
世の中は決して変わりません。
死の瞬間、池田は何を考えたのか。
それを考えてみることも、私たちの宿題だ。