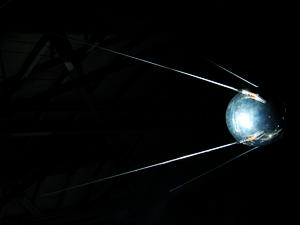一休さんの話 一
一休は、六歳のとき、
禅宗の名刹、安国寺に入った。
寺の書庫を常の住処とし、仏典に没頭。
座禅に励む日々を重ねた一休の眼に、
だんだん現実が見えてくる。
僧侶どうしの言い争い。
「自分は源氏の出である」
「わたしは公家の血筋である」
少年一休は、一編の漢詩をつくり、
これを批判する。
「法を説き 禅を説いて 姓名を挙ぐ
人を辱しむるの一句」
仏門に帰依した身で、現世の出自を
自慢しあう。恥ずかしいの一言だ。
一休の失望は日増しに深くなっていく。

murata
一休さんの話 二
一休は、十七歳のとき、
謙翁 (けんおう) という僧に出会う。
西金寺 (さいこんじ) という
苔むした貧乏寺にあって、
政治にすり寄らず、権威におもねず、
純粋禅として孤高の道をゆくその姿に、
一休は心打たれる。
この方こそが、
自分の求める禅の師匠だ。
一休は、雨露をしのぐていどの
粗末な寺に住み、
謙翁とともに街を歩く。
托鉢だけで暮らしたため、
日々の食事にも事欠く始末。
清貧のなかで、
謙翁の指導は峻烈を極めた。
一休は、禅の真髄に近づいていく。

一休さんの話 三
一休は、父を知らない子どもだった。
母とも、六歳のときに別れたきりだ。
母は、伊予の局という名の
やんごとない姫だった。
藤原一門の公家、日野家に生まれ、
御所にあがっていた。
父は、その伊予の局に手をつけた
後小松天皇そのひとではないか。
という、まことしやかな御落胤説がある。
長くつづいた南北朝の争いは、
後小松帝在位のとき、統一を見た。
以後、南北、交互に帝位を継いでいく、
という約定が交わされた。
一休が生まれた1394年は、
そんなナーバスな出来事の渦中にあった。
幼い一休が寺に出された背景にも、
どこか、きな臭い空気が漂っていた。

一休さんの話 四
あるとき、将軍・足利義満が
一休を試すべく、無理難題をもちかける。
「屏風の絵の虎が毎晩抜け出して
往生している。虎を縛ってくれないか」
一休は縄を持って屏風の前に立って言う。
「では虎を捕らえましょう。どなたか、
屏風から虎を追い出してもらえませんか」
少年一休の利発さを伝える、この種の挿話は、
江戸時代になって『一休噺』として集められ、
「とんちの一休さん」が一人歩きしていく。
だが、室町の乱世にあった現実の一休は、
幕府の庇護をかさに権威を振りかざす
禅宗に対する批判者として生きた。
ボロボロの法衣をまとい、なぜか、
腰に朱塗りの木刀をぶら下げていた。
生の魚も食らう。飲み屋にも花街にも通う。
法事の場でお経を唱える代わりに、
おならをして顰蹙を買ったりもした。
表では澄ました顔で仏法を説く坊主が、
裏では生臭い振る舞いに及んでいる。
一休はその放蕩無頼によって、
身をもって僧侶の腐敗を天下にさらした。
そんな意図を察した名もなき庶民は、
一休を生き仏と崇めるようになる。

一休さんの話 五
一休は、七十七歳のとき、恋に落ちる。
森(しん)、という名の、盲目の美女だった。
ふたりは小さな庵で同居を始める。
一休が遺した『狂雲集』という漢詩集に、
森との交情が謳い込まれている。
「森也 (しんなり) 深恩 (ふかきおん) 若 (も) し忘却せば
無量億却 畜生の身」
森の深い愛情を忘れたら、未来永劫に
畜生道に堕ちるでしょう、と。

crowbot
一休さんの話 六
一休は、ある年の正月、杖の先に
髑髏をぶらさげ、「ご用心、ご用心」と
唱えながら街を練り歩いた。
こんな歌を遺している。
「門松は冥土の旅の一里塚
めでたくもあり めでたくもなし」
元旦生まれのせいでもあるまいが、
めでたいめでたい、とひとが笑う日に、
一休は、人生の無常をつねに思っていた。
1481年、一休、死す。享年八十八。
臨終に際してこう呟いたと伝わる。
「死にとうない」
生涯、飾らず、奢らず、悟らず、
ありのままを生きた一休らしい、
未練の呟き。