
Festival Karsh Ottawa
グレン・グールドというピアニストが、いた。 ①
1964年以降に生まれたひとは、
グレン・グールドが
生でピアノを弾く姿を見たことがない。
なぜなら、1964年、このピアニストは、
コンサート活動のいっさいから
身を引いてしまったから。
かれは、1946年、まだ14歳のとき、
トロント交響楽団と共に舞台に立った。
クラシックの世界において、
早熟の天才は決してめずらしいものでは
ないけれど、しかし、かれの場合、
早くから芽生えた
コンサートに対する疑問が、
その後の生きかたを
きわめてユニークなものにした。

Piano Piano!
グレン・グールドというピアニストが、いた。 ②
32歳のとき、ライヴ演奏から
ドロップアウトしたグレン・グールドは、
50歳で亡くなるまで、
どんなに請われてもコンサートへの
出演を断わりつづける。
けれども、こんにち、
われわれは、スタジオにおかれた
一台のスタンウェイに向かうかれの姿を、
映像で見ることができる。
何本もドキュメンタリー映画ができるくらい、
グールドが残した映像は数多く存在する。
床上35.6cmという、異様に低い椅子。
猫背で前のめりになったグールドの
顔と手の距離がきわめて近い。
ピアノにすがりつくように構えた両肘は、
鍵盤よりも下に位置している。
その独特のフォームについて、
レナード・バーンスタインはこう言った。
「まるでかれ自身がピアノになろうと
しているように見えた」

patte-folle
グレン・グールドというピアニストが、いた。 ③
1955年、
22歳のグレン・グールドは、
コロムビアレコードで
バッハの『ゴルトベルグ変奏曲』を録音する。
これがレコードデビューとなった。
よりによって、『ゴルトベルグ』か。
なんの山場もない、ややこしいだけの
アリアの変奏曲じゃないか。
プロデューサーは選曲に反対した。
ピアニストは、この曲にこだわった。
グールドは、6月にもかかわらず
マフラーを巻いてオーバーを着込み、
手袋をして録音スタジオにあらわれた。
いきなり洗面所にこもって、
両手を30分もお湯につけたまま出てこない。
ピアノの前に坐ったかと思えば
いきなり奇声を発したり、
スタジオの中をうろうろと歩き出して、
ぷいっと外へ出てしまう。
やがて首を激しく振りながら戻ってきて、
何の前触れも合図もなく演奏が始まる。
その手首が、飛び魚のように鍵盤上を
飛び跳ね、うつくしい音がやってきた。
録音室にいた誰もが唖然として、
音に酔いしれた。

グレン・グールドというピアニストが、いた。 ④
グレン・グールドは、
聴衆の存在は、音楽の邪魔である。
とまで言い切った。
そんなかれについて問われた、
ほかのピアニストたちは、
たいてい、やや当惑ぎみに小声で言い添える。
けれど、観客との一体感から生まれる歓びは
ピアニストにとってなにものにも代えがたい、と。
グレン・グールドは違った。
やりなおしのきかないライヴ演奏では、
理想の音楽がつくれない。
スタジオなら、納得いくまでテイクを録って、
最良の演奏が選べるではないか。
かれは、繰り返し、そう主張した。
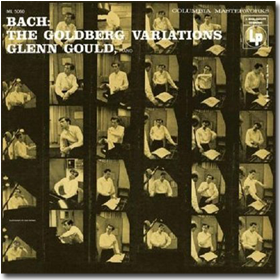
グレン・グールドというピアニストが、いた。 ⑤
映画『羊たちの沈黙』に登場した殺人鬼、
ハンニバル・レクター博士が、
娘を誘拐された上院議員に情報を提供する
見返りに、ある音楽テープを要求する場面がある。
レクターが欲しがったのは、
グレン・グールドの『ゴルトベルグ変奏曲』。
ヨハン・セバスチャン・バッハが
2段鍵盤付きのチェンバロのためにつくった
『アリアと種々の変奏曲』。
不眠症に悩んでいたある貴族の依頼で作曲し、
バッハの愛弟子であるゴルトベルグが
演奏したため、『ゴルトベルグ変奏曲』という
通称で知られるこの曲。
おなじアリアが、30もの変奏で、
微妙に描き分けられる複雑さと長大さ。
ピアノではなく、チェンバロのための曲だった
こともあって、弾きこなすのは容易ではない。
あるピアニストは、こう言う。
誰もグレン・グールドのように
『ゴルトベルグ』を弾くことはできない。
せめて、指が6本ほしい、と。
ちなみに、映画では描写が避けられたが、
『羊たちの沈黙』の原作となったトマス・ハリスの
小説において、レクターは左手だけ、
指が6本あったとされている。
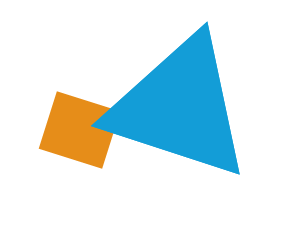
グレン・グールドというピアニストが、いた。 ⑥
グレン・グールドは、
夏目漱石の『草枕』の愛読者だった。
ラジオの番組で朗読までしているから、
相当な入れ込み方だ。
「四角な世界から常識と名のつく一角を
摩滅して、三角のうちに住むのを
芸術家と呼んでもよかろう」
といった部分に、グールドは深く共感していた。
「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。
意地を通せば窮屈だ。とかくこの世は住みにくい。
住みにくさが高じると、安い所へ引っ越したくなる。
どこへ越しても住みにくいと悟った時、
詩が生まれて、 画(え)が出来る」
冒頭の、あまりに有名なこの一節は、
グレン・グールドの生きかたそのものに
思えてくる。

グレン・グールドというピアニストが、いた。 ⑦
グレン・グールドの録音に
耳を澄ますと、うなり声が聞こえる。
うなり声というより、主旋律を歌う、
グレン・グールドの鼻歌だ。
グレン・グールドのスタジオ録音は、
聴衆のいないライヴ録音のようなものだ。
かれの息づかいが生々しく刻まれている。
CDジャケットの裏に、こう書いてある。
『グールド自身の歌声など、一部ノイズが
ございます。どうかご了承ください』

グレン・グールドというピアニストが、いた。 ⑧
グレン・グールドは、よくひととぶつかった。
レナード・バーンスタインとは、
ブラームスの協奏曲第一番の解釈をめぐって対立。
演奏会の冒頭で、バーンスタイン自身が、
じぶんはグールドの演奏に賛成しかねる、と
表明してから指揮をはじめる、異例の事態を招いた。
クリーブランド管弦楽団の指揮者、
ジョージ・セルは、リハーサルのとき、
30分間も椅子の高さを調整していたグールドに、
激怒。指揮棒を放り投げてしまう。
けれど、バーンスタインはその後、
「グールドより美しいものを見たことがない」
と、グールドの才能を認め、
セルも、「あいつは変人だが、天才だよ」と脱帽。
グレン・グールドとの
うつくしい共演盤を残したヴァイオリニスト、
ユーディ・メニューインは、こう言った。
「結局、かれは正しかった。」
























