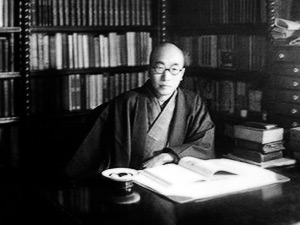あした、10月13日。
この「五島のはなし」の20回目を書いてくれた鳥巣くんが
五島で結婚式をあげます。
祝!鳥巣くん。そして新婦の優さん。
Vision執筆者である小野さんや三島くんもお祝いのために五島に上陸するようです。
五島の皆さま、新郎と新婦を見かけたら、ぜひ一声かけてあげてもらえませんか。
五島が好きで、五島で結婚式をあげる、というのです。うれしいじゃありませんか。
ぜひ、祝福してあげてください。
また、ぼくの会社の友人たちもお祝いのために五島に集結しています。
へんな一団を街で見かけたら、アガダナンバシヨットカ
と一声かけてやっていただければと思います。
いやあ、それにしても、めでたい。