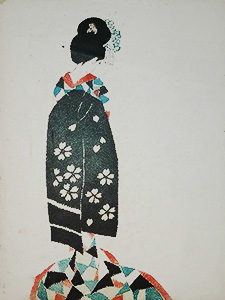
夢二の手紙4
竹久夢二の手紙
秀子へ
こんなにまた、切ないやりとりをする自分を
少しあわれに思う。
秀子は、なんとも言って来ない。
もしや、病気かしらともおもう。
また今日も植木をいじろう。
こんなときに、なんにも出来ない。
夢二の手紙は日記のようだ。
でも、この日記は返事を欲しがっている。
これが恋文というものかもしれない。
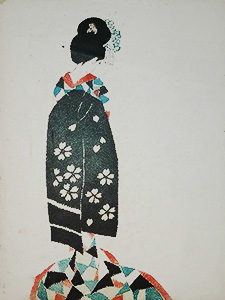
夢二の手紙4
竹久夢二の手紙
秀子へ
こんなにまた、切ないやりとりをする自分を
少しあわれに思う。
秀子は、なんとも言って来ない。
もしや、病気かしらともおもう。
また今日も植木をいじろう。
こんなときに、なんにも出来ない。
夢二の手紙は日記のようだ。
でも、この日記は返事を欲しがっている。
これが恋文というものかもしれない。

夢二の手紙 5
竹久夢二の手紙
嘆くようにぼそぼそ降ってきた雨が
いまはもうこらえきれないで、
大きな涙を流して泣き叫ぶように降ってきた。
寂しい寂しい、心のやりばがない。
じっとこらえていると涙がこぼれそうでならない。
泣けばなぐさむ心なら、泣きたいと思えど
ただもうもだもだと泣くに泣かれぬ。
たったひとりの夜は更けてゆくけれど
戸をたたくものは雨の音ばかり。
なんにも聞かいでも、なんにも言わいでも
ひと目顔が見たい、逢いたい。
いつの手紙かわからない。
誰に宛てたのかもわからない、竹久夢二の手紙。
思い通りにならない恋の相手は誰だったのか。
凜とした強い瞳の持ち主か、世間を恐れる気弱な少女か。
夢二の描いた女の絵をもう一度眺めてみたくなる。
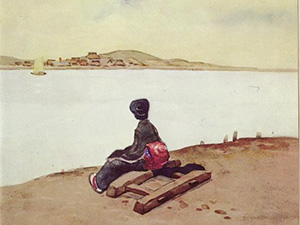
夢二の手紙 6 まあちゃん
竹久夢二の手紙
まあちゃんは今頃起き出ているであろう。
そして僕の手紙を読んでいるであろう。
まあちゃん、本当に早く帰って逢いたいねえ。
いま汽車は比叡の麓を通っている。
青い麦の間を青色の日傘をさして近江の少女がゆく。
湖は紫色をして、桃色の帆船を浮かべている。
夢二が「まあちゃん」と呼んだのは
離婚した妻、環(たまき)のことだった。
別れてもなお、夢二は年上の妻に甘える。
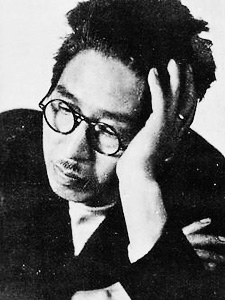
夢二の手紙 7 老詩人
竹久夢二の手紙
まさ子さん
私は手紙をあなたへ書きたくなったのです。
ところが、その気持ちで書いたら
きっとあなたは笑い出すか、あくびをするでしょう。
どちらにしても老詩人の愚痴に過ぎないと思うでしょう。
それほどあなたは若くて美しいのです。
「老詩人」と自分を呼ぶようになっても
夢二は恋をあきらめようとはしていない。

夢二の手紙 8 お葉と呼ばれた女
竹久夢二の手紙
おれの人形は美しくてなつかしい。
やはりなんといってもおれのものだ。
けれど、この人形のからだのどこかに
おれにわからないものがひそんでいる。
35歳の夢二が出会った理想のモデルは15歳だった。
夢二は彼女にお葉という名前をつけ
自分の好みに仕立て上げようとした。
6年一緒に暮らして、お葉は夢二のもとを去った。
それを呼び戻そうとする夢二の手紙には
お葉のことをおれの人形と書いている。
上のムービーは五島の教会のイルミネーションです。
クリスマス頃にはこんな感じになるみたいです。
中村直史くんが以前の記事で
五島で結婚式をあげたい。
そう思っているカップルが僕は好きです。
ふたりで五島を旅したい。
そう思っているカップルも僕は好きです。
と、書いてあったので教会をさがしてみたんです。
五島で結婚式といえばやっぱり教会かなあと思って。
HPをひとつ開いただけで31の教会が(厳密には29ですが)紹介されていました。
http://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/junrei/
手遅れの人はしかたないですが
これからの人、ぜひ五島で結婚式をどうぞ(玉子)

麦わら帽子 1 西条八十
西条八十 「帽子」
母さん、僕のあの帽子どうしたでせうね?
ええ、夏、碓氷から霧積(きりづみ)へゆくみちで、
谿底へ落としたあの麦藁帽子ですよ。
母さん、本当にあの帽子どうなったでせう?
そのとき傍に咲いていた車百合の花は、
もうとうに枯れちゃつたでせうね。
そして、秋には、灰色の霧があの丘をこめ、
あの帽子の下で毎晩きりぎりすが鳴いたも知れませんよ。
標高1000メートルの山道から谷底に向かって飛ぶ
西条八十の麦わら帽子。
詩人が描き出した一枚の絵は、日本人の心にいまも残る。

違いがわかる男
麦藁帽子 2 立原道造
立原道造 「麦藁帽子」
八月の金と緑の微風(そよかぜ)のなかで
眼に沁みる爽やかな麦藁帽子は
黄いろな 淡い 花々のやうだ
甘いにほひと光とに満ちて
それらの花が 咲きそろふとき
蝶よりも 小鳥らよりも
もつと優しい愛の心が挨拶する
わずか7行のこの詩は
いままでに8人の作曲家によってメロディをつけられ
独唱曲や合唱曲に仕立てられている。
その歌をきくと
立原道造が愛した軽井沢の幸せな夏が浮かぶ。

Fx
麦藁帽子 3 寺山修司
寺山修司 麦藁帽子のうた
海を知らぬ 少女の前に麦藁帽の
われは両手をひろげていたり」
わが夏を あこがれのみが駆け去れり
麦藁帽子被りて眠る
列車にて 遠く見ている向日葵は
少年のふる帽子のごとし
ころがりし カンカン帽を追うごとく
ふるさとの道駈けて帰らん
寺山修司の麦藁帽子はふるさとの匂いがする。
「もしかしたら私は憎むほど故郷を愛していたのかもしれない」と
寺山自身が書いている、そのふるさとである。

麦藁帽子 4 堀辰雄
堀辰雄 「麦藁帽子」
お前はよそゆきの、赤いさくらんぼの飾りのついた、
麦藁帽子をかぶっている。
そのしなやかな帽子の縁が、私の頬をそっと撫でる。
私はお前に気どられぬように深い呼吸をする。
しかしお前はなんの匂いもしない。
ただ麦藁帽子の、かすかに焦げる匂いがするきりで。
……私は物足りなくて、
なんだかお前にだまかされているような気さえする。
堀辰雄の短編小説「麦藁帽子」の主人公は
15歳と13歳の少年と少女。
少女は友人の妹だった。
やがて、海辺の村で一緒に夏休みを過すことになるが
少女はまだあどけなく、少年の思いが届かない。
「麦藁帽子」に描かれた淡い恋の舞台は千葉の海岸で
中学生だった堀辰雄は数学が好きな少年だった。

posterboy
麦わら帽子 5 芥川龍之介
芥川龍之介の「麦わら帽子」
この標準を用ひずに、
美とか真とか善とか言ふ他の標準を求めるのは
最も滑稽な時代錯誤であります。
諸君は赤らんだ麦藁帽のやうに旧時代を捨てなければなりません
芥川龍之介「侏儒(しゅじゅ)の言葉」の文章である。
その内容はともかく
「赤らんだ麦藁帽のように旧時代を捨てなければ」という言葉が
印象深い。
陽に焼けて色が変わった麦藁帽は
おしゃれではないのだ。
芥川龍之介は麦藁帽子の似合う作家だった。
その最後の写真に
芥川は麦藁帽子にくわえ煙草で写っている。

matley0
麦藁帽子 6 北原白秋
北原白秋の「麦わら帽子」
麦藁帽子にトマトをひとつ
抱えて歩けば 暑いよおでこ
北原白秋の童謡「トマト」は
夏の絵の具で描かれた絵本のようだ。
赤いトマトと麦わら帽子
あとの風景は
真夏の昼下がりの暑い日差しに
白くかすんでいる。

paloetic
麦わら帽子 7 中原中也
中原中也の「麦わら帽子」
愛するものが死んだ時には、
自殺しなけあなりません。
愛するものが死んだ時には、
それより他に、方法がない。
けれどもそれでも、業が深くて、
なほもながらふことともなつたら、
奉仕の気持に、なることなんです。
奉仕の気持に、なることなんです。
テムポ正しき散歩をなして
麦稈真田(ばっかんさなだ)を敬虔に編み――
まぶしくなつたら、日蔭に這入り、
そこで地面や草木を見直す。
この詩に出てくるバッカン真田とは
麦藁を平たく編んだものをいう。
麦わら帽子はバッカン真田からつくられる。
バッカン真田を編むのは、意志も想像力もない単純な仕事だ。
2歳の息子を亡くした中原中也は
自分をなくすことによって生きようとしている。

暑い。二匹の猫の食欲がない。
それでも夜になったら食べていたのだが
数日前から黒い愚猫(黒兵衛♀)が夜も食べなくなった。
医者へ連れて行った。
血液検査をした。これといって悪いところはない。
点滴をした。
帰宅後、やたらと階段を上り下りしている。
さすが愚猫である。
用もないのに階段をズダズダと上がっては下りて
せっかくの点滴養分を無駄に使っている。
その養分が切れたとみるや、
暗い狭いところでまたじっと垂れ込めている。
まったく愚猫である。
病猫(ハエタロー♀)は
夜中から散歩だ散歩だと鳴き喚き
朝になるのを待ちかねて飯も食わずに出かけていく。
見ると、庭の蛇口の下あたりでぐったりと寝ている。
ちっとも散歩ではない。
ほぼ一日中日陰なのでいくぶん涼しいのだろう。
出かけるときはそれを取り込んでから出るのだが
こちらはまだステロイド効果の持続期間内なので
夜になって涼しくなるとなんとか食べてくださる。
こう暑いと家の中の猫も気の毒だと思って
エアコンを夕方までのタイマーにして出るのだが
猫は涼しい部屋にはいない。
階段、玄関、風呂場のどこかで寝ている。
たいへん空しい。
愚猫も病猫もいい加減にしてもらいたい(玉子)

夜、大きな猫が塀から庭に侵入しようとしていた。
見かけない猫だな、どこの猫だ。
ちらっと顔が見えた。鼻が獅子鼻だった。
おかしいな…
さらによく見たら鼻から額にかけて白い筋があった。
猫じゃない、断じて猫ではない。
なんてったっけ、これ。中国のやつ。
そうそうそう、ハクビジン。違うよ、ハクビシンだよ。
カメラカメラ。
大騒ぎで写真を撮った。
ちっとも怯えない。悠々としているし
むしろ人を歓迎しているようにも見えた。
飼われて捨てられたのか、脱走したのか知らないが
どうもうちのあたりには
野良化したハクビシンが何頭も生息しているらしい(玉子)

Copyright ©2009 Vision All Rights Reserved.