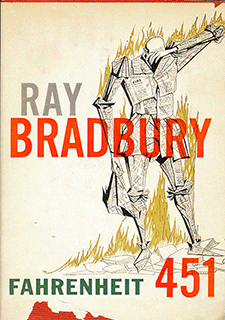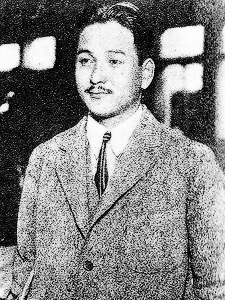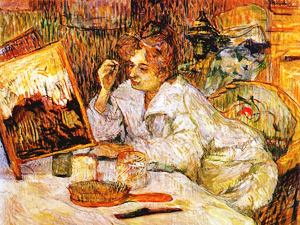Ian Britton
「旅する言葉・チェコ」カレル チャペック
「園芸家12ヶ月」「ダーシェンカ」で知られる
チェコの国民的作家カレル チャペック。
彼はジャーナリストとしても活躍していた。
そして数多くの旅行記を出版している。
1925年にふるさとチェコについても書いていた。
塔はチェコの特産だ、と私は言いたい。
わが国のあのような不思議なキューポラ、
まるっこい玉ねぎ型、けしの頭型、
灯台、付属塔とギャラリーと尖塔は、
ほかの場所にはないからである。
チェコの古い町はどこでも、
その町に特有の塔を持っている。
プラハは、百塔の町とも呼ばれている。
90年近く経った今でも、チェコの特産は健在だ。

Jean-Pol GRANDMONT
「旅する言葉・ふるさと」カレル チャペック
チェコの国民的作家カレル チャペックは、
幼少の頃、父の仕事の関係で幾つかの地に移り住んだ。
彼がふるさとについて書くとき、
それは特定の場所ではない。
生まれ故郷、またはより正確に言えば、
私たちが子どもの頃の何年かを過ごした地方は、
決して地理的な地域ではなく、
私たちが小さかったときに関係した
数多くの場所や、秘密の隠れ家なのだ。
こおろぎやとかげをつかまえた畦道。
水浴びをした場所。
よじ登って腰掛けた、とねりこの木。
実を盗みにいった桃の木。
それは自分だけの特別な秘密。
大人になってその地方を訪れた彼は、
思い出の場所は、どこかに行ってしまったことを知る。
それは生まれ故郷だった。
わたしは感動しながらも、がっくりしていた。
もはやそこは、世界のすべてではなくなっていたのだ。

bjoern.f
「旅する言葉・モルダウ川」カレル チャペック
ヴルタヴァ川。
チェコの国民的作家カレル チャペックが、
青春時代を過ごしたプラハをゆったりと流れている。
ドイツ名、モルダウ川。
チャペックはその「ヴルタヴァ川」の美しさを
音楽や絵画や散文、詩で描写した人はいない、と嘆いている。
春の陽光の中で清らかに輝き、
明るく音高く、おごそかに、まろやかで楚々とした、
あの青春時代の乙女のような姿を。
または、たそがれどきのプラハへ注ぎ込む、
限りなく青く明るく誇らしげな
プラハのあかりの列を映して、
繻子のような、ブロケード織りのような、
燃えるような輝きを見せるその姿を。
川の描写はまだ続く。
すべての景観をしのぐ景観、美の中の美、
プラハの空や宮殿、庭園、
この地の美しい景観のすべてをともなった、
プラハ全体のなかでも最高の魅力を。
チャペックは「ヴルタヴァ川」の美しさを描ききった
最初の一人になったのだ。

Zaqarbal
「旅する言葉・スペイン」カレル チャペック
21年間のジャーナリスト生活を通じて、
カレル チャペックは、ヨーロッパ各国を旅した。
1929年にスペインを訪れたとき、
チェコとはまるで違う彼の地の魅力を
「別の大陸のようだ」と表している。
マドリードは宮廷のパレードと革命のスコールの町だ。
空気は軽く、いささか興奮をかきたて、スリルに満ちている。
それに反し、セビリアは祝福に満ちてけだるく、
バルセロナは、なかば秘められた状態でわき返っている。

José-María Moreno García
「旅する言葉・トレド」カレル チャペック
古都トレド。
世界遺産にも指定されているこの街は、
城壁に囲まれ、狭い石畳の路地が迷路のように入り組んでいる。
カレル チャペックも、この街を訪れたとき、
その歴史的建造物と狭い路地に魅せられた。
ジグザグに曲がったアラブ風の小道をさまよい歩いていく。
あなたは七歩ごとに立ち止まることになるだろう。
西ゴート族の柱があると思えば、モサベラ人の壁がある。
奇蹟の聖母マリア様もいらっしゃる。
ムハデル人の塔、ルネッサンス風の宮殿があり、
左右に耳をひろげたロバも通り抜ける。
そして、大聖堂については、たしかにそこへは行ったのだけれど、
さだかではないと言う。極めて多くの品、
多様な宗教美術を目にしたあまり、夢を見ていたかのようだったと綴る。
あまりにも多くのトレドの名物を目のあたりにしたチャペックは、
こう結論づける。
この世で最良の博物館は、生きた人々の街路だ。
ここはまるで、別の時代に迷いこんだような感じがする、
と誰もが言いたくなるだろう。
だが、それは適切ではない。実際はもっと不思議なものだ。
別の時代ではなく、過去にあったものが現存していることなのである。
民族の独自性と多様性をそのまま受け入れることの大切さを
彼は伝えようとしているのだ。

wildphotons
「旅する言葉・オランダ」カレル チャペック
チェコの国民的作家でありジャーナリストであり、
園芸家でもあるカレル チャペック。
1931年、彼は国際ペンクラブの会合でオランダを訪れる。
そして世界で最も綺麗な庭、
オランダのかわいらしい家々の庭を見て、
自分の庭に、この土壌と湿度があれば死にものぐるいで
世話をするだろうと書いている。
しかし、オランダで一番気に入ったのは、人の住居だ。
驚いたのは、人々がいかに家と街路を結びつけているか、
ということだった。
窓の前には何も囲う物のない庭があり、
その広い、磨かれた窓は覆う物もなく、
通行人たちは誰でも、その家の灯の下にある、
家族の豊かさと模範的な生活を見ることができる。
その暮らしの清潔さと自然さに嫉妬を抱きながら、
チェコ人に数百年与えてくれれば、
その暮らしに近づけるのにと、渇望する。

Jesper Hauge
「旅する言葉・ノルウェー」カレル チャペック
カレル チャペックの最後の旅行記は「北への旅」。
デンマーク、スウェーデン、ノルウエーへの旅だった。
ノルウェーからは船で北極圏をとおりフィヨルドを見学している。
その船旅の途中、漁師たちの島にそばを通り過ぎる。
ドゥーノヴィの漁師たちの島だ。
むき出しの丸っこい岩ばかりで、
ただ少しばかり緑がふりかけられている。
こころは恐ろしくさびしい所だ。
家は一軒しかない。
ただ小型の船と海、それ以上は何もない。
この地で人間は、英雄となるために戦う必要はない。
生きていくだけで十分なのだ。

タカ
「旅する言葉・帰途につく」カレル チャペック
カレル チャペックは、数々の旅行記を出版したが、
旅に出かけたくないと言う。
外国にいると、自分がお払い箱にになった気がすると言うのだ。
旅に出ることを断る言い訳が思いつけなかっただけだ、と。
そのくせ、旅の帰りに、もっといろいろなものを
見なかったことを悔やんでいる。
旅行者が持つ最初の印象は
世界のどの地域に行こうともすべて同じだ。
しかしその後、旅行者が持つ最終的印象は、
世界は限りなく多様でどの地域もそれぞれ美しい、
ということになる。
だが、そんな印象に達するのは、
ふつうはもはや手おくれになった時で、
帰りの列車で、何を見たのか、
もはやゆっくりと忘れかける時なのだ。
旅に出ることは、世界を知ることなのだ。
小国チェコの国民的作家は、そのことを知りつくし、
さまざまな民族と出会うことを楽しんでいた。