古居利康 12年10月14日放送

もうひとりのわたし 渡辺昇の場合
渡辺昇は、「安西水丸」になる以前、
絵本を一冊出している。
渡辺昇著、『夏の終わり−少女』。
1969年、限定300部、自費出版。
「安西水丸」の本名、渡辺昇は、
村上春樹の、1985年以降の小説の中で
本人とは別の世界を生きていく。
『ファミリーアフェア』という短編では、
主人公の妹の婚約者。
『双子と沈んだ大陸』では、翻訳会社の共同経営者。
『象の消滅』では、動物園の象の飼育係。
『ねじまき鳥と火曜日の女たち』では、
猫の名前であり、妻の兄の名前でもあった。
どう考えても同一人物ではない、
カタカナの「ワタナベノボル」。
あたかも「渡辺昇」という俳優が、
いろんな役柄を演じるように登場した。
『「ワタナベノボル」という名前には、
普通じゃないものを感じる。』
『村上朝日堂』や『夜のくもざる』といった仕事で
コンビを組むことの多い安西水丸に、
村上春樹はそう語ったという。
その後、「ワタナベノボル」は、
『ノルウェイの森』においては
「ワタナベトオル」に変化し、
『ねじまき鳥クロニクル』においては
「ワタヤノボル」に変貌し、
村上春樹における「ワタナベノボル」時代の
終焉を告げている。
古居利康 12年10月14日放送

葱
もうひとりのわたし 樋口奈津の場合
いまでは、名前と言えば、
苗字と名前をあわせて姓名とするのが
あたりまえだが、江戸時代までは、
苗字をもたないひとの方が多かった。
明治の世になって
誰もが苗字を持つことになっても、
女性だけは苗字を用いる習慣があまりなかった。
結婚すれば変わってしまうものを、
嫁入り前の娘が用いるべきでない、と考えられた。
後世、「樋口一葉」として知られる女性作家は、
原稿にただ「一葉」と署名した。
戸籍名、樋口奈津。
「一葉」は、ダルマさんに由来する。
と言うと、なぞかけのようだが、
経済的に困窮していた樋口家のことを
「お足がない」と引っかけ、
手足のない達磨大師が、一枚の葦の葉に
乗って中国へ渡った伝説になぞらえた
と伝えられる。
古居利康 12年10月14日放送

もうひとりのわたし 山田梨紗の場合
樋口一葉が亡くなってから、
約100年後に生まれた山田梨紗は、
「綿矢りさ」という名前で
小説家になった。
「綿矢」という苗字は、
高校の同級生の名前を参考にした。
「一宮りさ」という別案もあったが、
姓名判断の結果、「綿矢」を採用した。
「綿矢りさ」は17歳でデビュー。
「樋口一葉」よりも3歳早く世に出た。
古居利康 12年10月14日放送

ROSS HONG KONG
もうひとりのわたし 色川武大の場合
色川武大は、
「阿佐田哲也」という名前で、
麻雀小説を量産した。
「阿佐田哲也」以前に、
麻雀小説というものは存在しなかった。
文章と文章の間に麻雀牌の状況図を挿入する
前代未聞の小説。
「阿佐田哲也」は、
関東で9番目に強いプロの雀師だったという。
欲望。駆け引き。やっかみ。裏の裏。
麻雀を題材にしながら、人間というものの
わけのわからなさを描いた。
そんな阿佐田哲也が、
本名である「色川武大」にもどって、
自伝的な小説を書き始める。
元海軍中佐だった父との確執。
ナルコレプシーという睡眠障害に悩み、
白昼夢のごとき幻覚に苦しむ狂人としての自分。
亡くなる直前、妻にこう言った。
「阿佐田哲也君をやれば、
なんとか生活はしのげるが、これからは
純文学一本に絞っていこうと思う。
オレにはもう時間がないんだ」
1989年、昭和の最後の年、
色川武大と阿佐田哲也はこの世を去った。
蛭田瑞穂 12年10月13日放送

食べる作家①太宰治
太宰治というと、
痩せぎすの小説家という印象があるが、
実は大食漢で旺盛な食欲の持ち主だった。
いちばんの好物は毛ガニで、
ある時、酔って新宿の街を歩いていた太宰は、
毛ガニをうず高く積んだ夜店を見つけると、
素手で一匹を掴み、
その場でムシャムシャ食べ始めたという。
ニワトリの解体も得意だった。
さばいたトリは骨付きのままぶつ切りし、
豪快にトリの水炊き鍋をつくった。
一方で繊細な面もあった。
箸の使い方が上手で、長い箸の先だけを使って、
きれいに魚を食べたという。
よく食い、よく飲む。
太宰はそんな作家だった。
蛭田瑞穂 12年10月13日放送

食べる作家②林芙美子
昭和5年に『放浪記』でデビューし、
一躍時代の寵児となった林芙美子。
芙美子はその翌年憧れのフランスに渡った。
パリに下宿を借りた芙美子は、
映画やオペラに通い、美術館を巡り、
花の都の生活を満喫した。
しかし、ただひとつ報われなかったのは
日本食への思いだった。
半年間の滞在を終えた芙美子は船で神戸に着くと、
すぐに港の近くの小さなうどん屋に行き、
葱を振りかけた熱いうどんを食べた。
天にものぼるやうにおいしい。
たつた六銭だつたのに吃驚してしまった。
うどんの味を芙美子は日記にそう記している。
蛭田瑞穂 12年10月13日放送

食べる作家③内田百閒
太平洋戦争真っただ中の昭和19年、
内田百閒は『餓鬼道肴蔬目録(がきどうこうそもくろく)』
という作品を書いた。
まぐろ 霜降りとろノぶつ切り
ポークカツレツ
シユークリーム
富山のますの早鮨
料理の名前だけが延々と列記されている風変わりな作品。
百閒はこの作品を
「食ベルモノガ無クナツタノデセメテ記憶ノ中カラ
ウマイ物食ベタイモノ物ダケデモ探シ出シテ見ヨウ」
と思いついたという。
百間の、食への執着心の、
なんとすさまじいことか。
蛭田瑞穂 12年10月13日放送
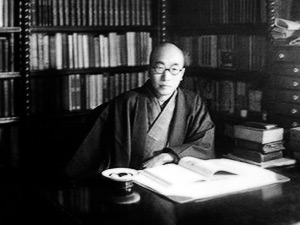
食べる作家④江戸川乱歩
江戸川乱歩が酒を飲むようになったのは、
50を過ぎてから。
当然、あまり強くはなかった。
日本酒を一合飲むと赤ら顔になった。
二合飲むと動悸が激しくなった。
三合飲むと心臓が苦しくなった。
詩人の堀口大學の家で日本酒をふるまわれ、
酔ってそのまま床に寝てしまったこともある。
そんな乱歩もビールは好んで飲んだ。
喉のかわいたときのビールは、むろんよろしい。
ビールでは、わたしには、つまみものよりも
薄く切った脂の多いトンカツに生キャベツが適薬である。
風呂から上ってこれをやるのは格別。
エッセイの中で乱歩はそう記している。
蛭田瑞穂 12年10月13日放送

食べる作家⑤幸田露伴
幸田露伴の文章に「供給会社」というものがある。
内容は、朝昼晩三度の炊事は面倒で
労働力の損失になる、
そこで、安い食事を供給する会社ができれば
非常に便利である、というもの。
そして露伴はこう続ける。
清潔で迅速で上品で、少しの虚飾もなく、
単に食事を要領よく出す。
こういう店をたくさんつくればいい。
大金を投じ、供給会社を各都市に設ければ、
個人にとっても都市にとっても甚だ有益であろう。
露伴の言う供給会社こそ現代における
ファミリーレストランやファストフード店。
露伴がこの文章を発表したのは明治45年。
その先見の明に驚く。
蛭田瑞穂 12年10月13日放送

食べる作家⑥坂口安吾
坂口安吾は無類の料理好きだった。
アンコウを丸々一尾用意し、身と肝を選り分ける。
残った部分は骨も一緒にすり潰して汁をとる。
この汁に味噌を混ぜ、身と肝とネギを入れて煮る。
アンコウ以外は味噌とネギを使うだけで、
一滴の水さえ使わない安吾流アンコウ鍋。
アンコウという名は安吾に通じる。
「共食いだ」と言って
安吾はアンコウを好んで食べたという。
























